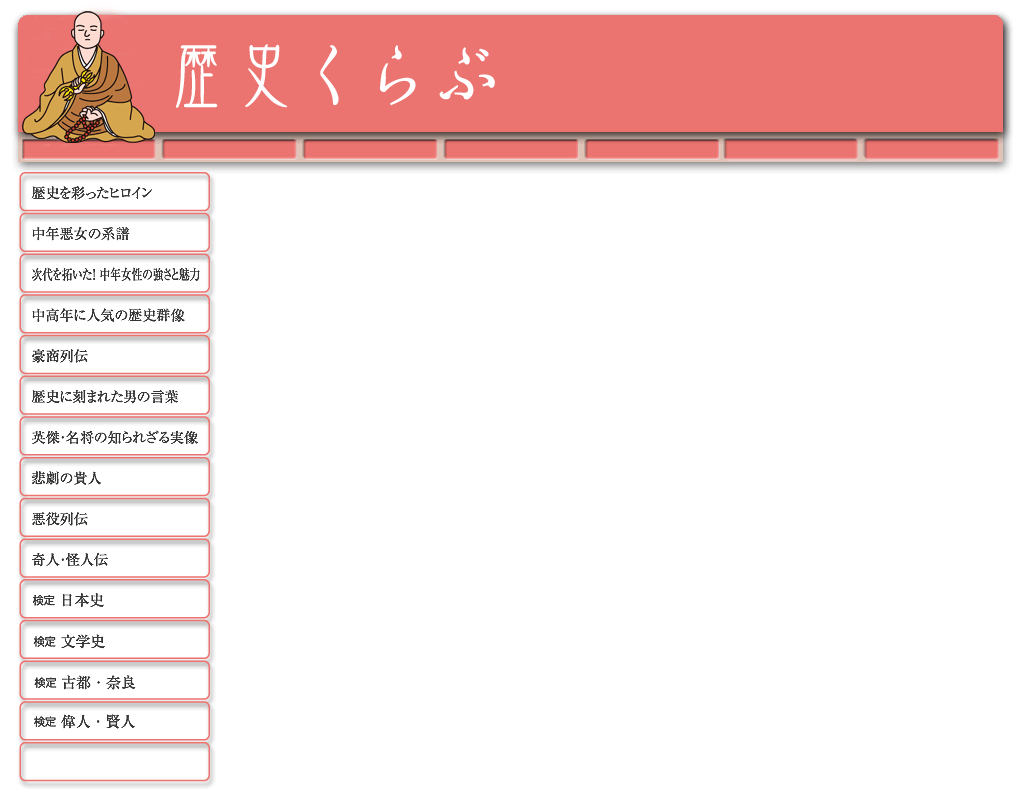
|
仏像ミニ知識
2) 日本の仏像の歴史 日本の仏像はいかにして進化していったのか? 飛鳥時代の仏像は、金銅仏が主流 原形をつくってから溶かした青銅を流し込んでつくり、最後に鍍金(ときん=金メッキ)をする。銅の部分を蜜蝋で造形するのが蝋型鋳造だ。平安時代以前は、10cmに満たない小金銅仏から丈六仏まで、この蝋型鋳造法でつくられた。東大寺の大仏の場合は蝋型鋳造ではなく、原形をつくり、外型と原形を削った隙間に銅を流し込む作業を8回に分けて行った。 奈良時代は究極のプロポーションを追求した仏像が求め、塑造、乾漆造が登場 塑像は塑土(粘土)を盛り上げてつくる、つまり粘土細工である。塑土のつきを良く、丈夫にするために、心木を立て、繩を巻き、その上に荒土、中土、雲母の入った仕上げ土の順に盛り上げ、形をつくっていく。最後に彩色または漆箔で仕上げする。 平安時代は一木造と寄木造の仏像が隆盛 脱活乾漆造(だつかつかんしつづくり)は、漆でつくられた張り子人形のようなもので、中が空洞になっている。原形を粘土でつくり、その上に麻布を漆で張り重ねていく。乾燥させてから背中などに窓を開けて中の粘土をかき出し、木枠に固定して、仕上げをする。細かい部分や微妙な表現は木屎漆(こくそううるし)を盛り上げて、彩色する。天平時代には盛んに造像され、興福寺の阿修羅像のような傑作が数多く残っている。 木心乾漆造(もくしんかんしつづくり)は、脱活乾漆像の塑土でつくられた原形の部分を木でつくり、そのまま空洞にしないで漆を盛り上げていく。心となる木造部分は、一木であったり複数材を使っていたりする。また、細部までほぼ完成段階に近く彫ってから漆を重ねる場合と、およその形だけで漆を重ねていく場合がある。奈良時代の後半以降、この木心乾漆造がほとんどとなった。 鎌倉時代は鎌倉仏師たちによる質実剛健な力強さが主流の仏教新時代へ 一木造(いちぼくづくり)とは、像の体幹部、つまり頭部と体部を一本の木から彫り出す木彫技法のこと。体幹部から離れた部分、腕や天衣などは別材を張り合わせる。檀像などでは、完全に一本の材からつくることもある。材の乾燥による干割れを防ぐために、内刳(うちぐ)りを施すこともある。奈良時代末期から平安時代前期の特徴的な木彫像。 寄木造(よせぎづくり)は、体幹部を複数材を寄せてつくる方法だ。内刳りを大きくするため一木造の途中の過程で、材を割り、内刳りを施してから接合する方法が9世紀には考案された。初めから体幹部を別材を寄せる寄木造は、より効率的に大きく内刳りをすることができる。平等院鳳凰堂の阿弥陀如来坐像をつくった定朝が完成した技法。 |