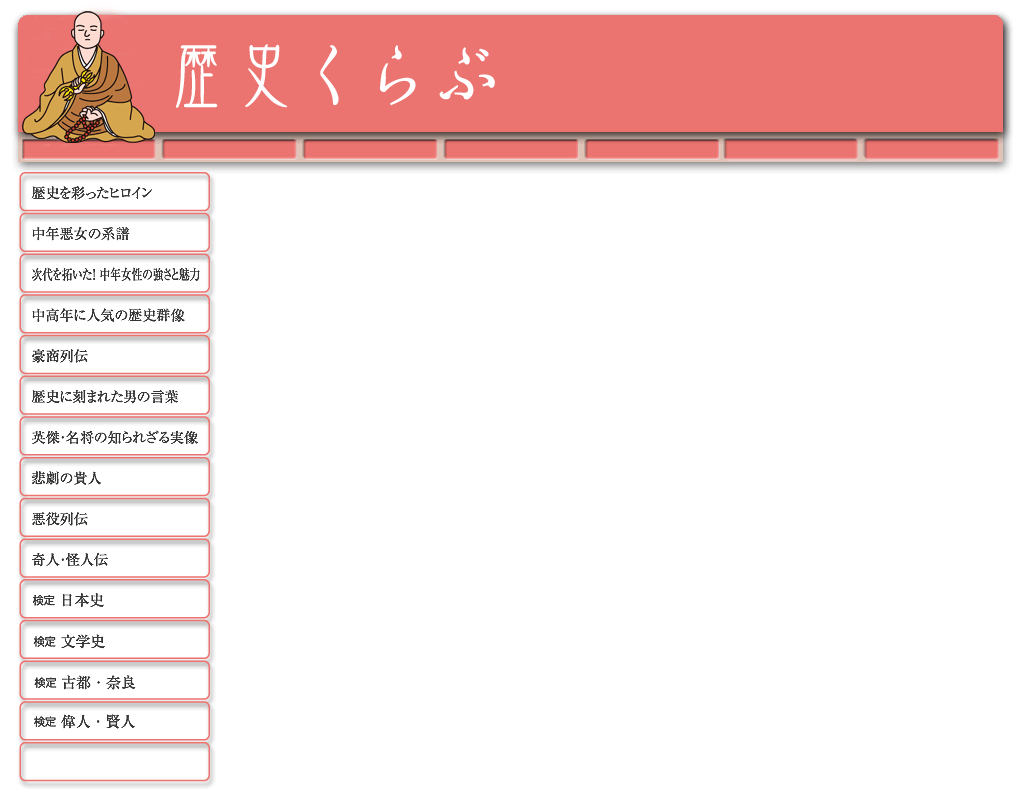
|
仏像ミニ知識
1) 仏像の見方 4「天」の特徴 ヒンドゥー教などの神々が仏教に取り入れられたのが「天」だ。他のグループが人々を悟りへと導き助ける役目をするのに対し、天は仏教の守護神の役割を果たし、現世利益的信仰を集める。天の姿は多種多様で鬼子母神など女性神まで揃う。大人気の「阿修羅」もこの部類に入る。大別すると、四天王、金剛力士(仁王)、十二神将など甲冑に身を固めた武装像と、吉祥天、弁才天(弁財天)などに代表される長い衣や中国風の服を着た柔和な姿の像があり、それぞれ個性が際立っているのが天の特徴。 仏敵を退散させるために、明王のように忿怒の形相を取ることが多く、手には剣や弓、斧、輪などの武器を持ち、災いや悪鬼を追い払う。また、武装像は沓を履いていることが多い。戦うときの必需品だったためだ。 梵天は帝釈天と並んで天の最高位にあり、梵天と帝釈天が対で安置される。帝釈天は、インド神話では最強の神であり、戦闘の神だった。釈迦の誕生や説法の場面で現れ、釈迦に従い釈迦を助ける。阿修羅と戦って、阿修羅を仏教に帰依させたエピソードは有名。 金剛杵を執る者という意味の執金剛神が、二体に分かれて寺門の左右に立ち、仏法を守るようになったのが、周知の金剛力士、あるいは仁王だ。口を開ける「阿形」と閉じる「吽形」の二体で、阿と吽は、万物の始まりと終わりを象徴している。相手と気持ちを合わせることを「阿吽の呼吸」という「阿吽」だ。 四天王は須弥山の中腹の四方に住み、それぞれの方角から仏土を守護する四人の神だ。堂内では須弥壇の四隅に安置される。東方・持国天(じこくてん)、南方・増長天(ぞうちょうてん)、西方・広目天(こうもくてん)、北方・多聞天だ。四天王は武器を取り、武装した忿怒形だ。持国天と増長天は剣、戟(げき)、鉾などを持つ。広目天は筆と巻物を持つことが多く、多聞天は宝塔を持つ。四天王は普通、一頭か二頭の邪鬼を足で踏みつけて、邪悪なものを退治しているが、岩座の上に立つこともある。四人で一セットなので、動きや表情に変化をつけ、四体セットとしてのバランスが考えられている。武将の配下や芸道の門下で、優れた四人を四天王と呼ぶのも、ここからきている。 八部衆は、古代インドの鬼神が釈迦に教化されて仏教とその信者を守るため、釈迦の眷属(けんぞく)となったものだ。十大弟子とともに釈迦の周りで説法を聴き、釈迦の涅槃のときにも登場して、釈迦を守る。天竜八部衆ともいい、天、龍、夜叉、乾闥婆(けんだつば)、阿修羅、迦楼羅(かるら)、緊那羅(きんなら)、摩_羅伽(まごらか)の八神だ。これらはいずれも原則として武装している。 十二神将は十二夜叉大将といい、薬師如来の眷属だ。薬師如来を敬う信者のために、一切の苦難を取り除こうと働く。宮毘羅(くびら)、伐折羅(ばさら)、迷企羅(めきら)、安底羅(あんてら)、額_羅(あにら)、珊底羅(さんでら)、因達羅(いんだら)、波夷羅(はいら)、摩虎羅(まごら)、真達羅(しんだら)、招杜羅(しょうとら)、毘羯羅(びがら)の十二人が、それぞれ武装して、武器を持ち、闘う姿勢で薬師如来を護持している。経典や作例により、持ち物や名称は一定していない。 二十八部衆は、千手観音に従う二十八人の眷属だ。それぞれが五百の眷属を従えるといわれる。千手観音と千手観音を信じる人々を守る役割を担う。武将形、天女形、獣面形と様々な姿を取っていて、天部の仲間勢ぞろいといえるほどだ。仁王(那羅延堅固王=ならえんけんごおう、密迹金剛力士=みつじゃくこんごうりきし)、四天王(東方天、毘楼勒叉天王、毘楼博叉天王、毘沙門天王)、八部衆(五部浄居天、難陀竜王、乾闥婆王、阿修羅王、迦楼羅王=かるらおう、緊那羅王、摩_羅迦王=まごらかおう、畢婆迦羅王=ひばからおう)、吉祥天(大弁功徳天)、鬼子母神(神母天)、大自在天(摩醯首羅王=まけいしゅらおう)、大梵天王、帝釈天などがずらりと並ぶ。さらに風神、雷神が加わることがある。俗人の女性の摩和羅女(まわらにょ)、地獄から罪人を連れて釈迦のもとに詣でる半裸の老人、婆藪(ばすう)仙人などバラエティに富むメンバーだ。 仏像の姿勢とその意味 仏像には様々なポーズがある。座っている「坐像」、立っている「立像(りゅうぞう)」、腰掛けている「倚像(いぞう)」、涅槃を迎える釈迦に見られる、横になった「涅槃像」などがある。それ以外にも、天高く舞い上がったり、泳ぐようなしぐさの飛天などがある。 坐像の基本となるのは、座禅をするときの座り方、結跏趺坐(けっかふざ)だ。これは気力を充実させる坐法であり、瞑想や救いの方法を考えているとき、また衆生を前にして法を説く姿を示す。右足が上の場合は吉祥(きちじょう)坐、左足を上に組む場合は降魔(ごうま)坐という。右膝を立てて座る形を輪王(りんのう)坐という。 立像はたいていの場合、どちらか一方の手を上げて、蓮華や水瓶(すいびょう)などを持つことが多い。立ち方は両足を揃えてまっすぐ立つものや、頭や腰を左右に曲げたものがある。手を上げ、腰をひねった格好の像は、上げた手と同じ側に腰を突き出すことが多い。片手を上げたときに、そちら側に腰が突き出るのは、自然な動作だが、このような動きが仏像にも取り入れられている好例だ。 両足を揃えて椅子に腰掛けた姿の倚像は、中国や西域の仏像ではよくみられるが、椅子に座る習慣がなかった日本ではあまり広まらなかった。 |