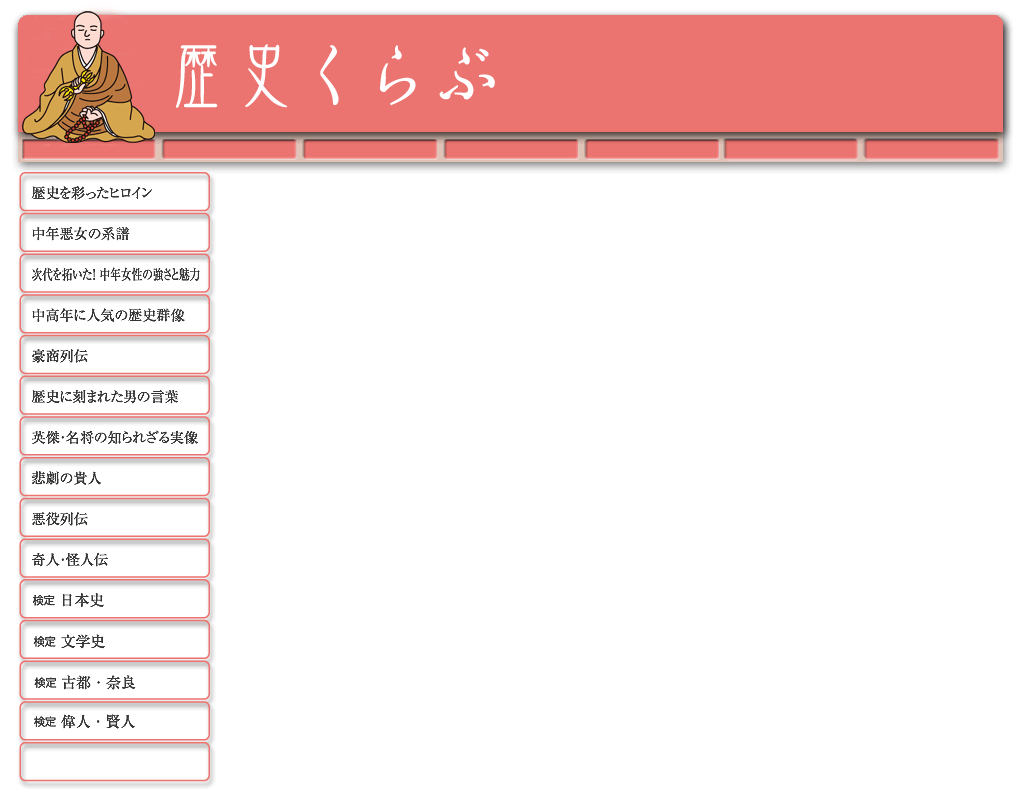
|
仏像ミニ知識
1) 仏像の見方 仏像の種類は 1. 如来 2. 菩薩 3. 明王・天−の3つに分かれる 仏像として最初に誕生したのは悟りを開いた釈迦の像で、釈迦如来と呼ばれる。「如来」は悟りを開いた人の意味で、仏像の最上位。次が出家前の釈迦をモデルにした修行中の「菩薩」で、その下に「明王」と仏教の守護神である「天」が続く。 1「如来」の特徴 如来とは「悟りを開いた人の意味、真理の世界からやってきた人」という意味で、仏界の最高位に位置する。その如来グループの代表が釈迦如来で、仏陀となった釈迦の姿を表している。出家して悟りを得た姿なので、華美な衣装や装飾品は身に着けず、たいていの場合、体に衲衣(のうえ)と呼ぶ布1枚だけを巻き付け、頭部は粒々だ。これが螺髪(らほつ)で、修行中に伸びた髪が縮れて丸まったもの。当初は釈迦如来だけだったが、大乗仏教で阿弥陀如来や薬師如来、大日如来などが誕生した。手には何も持っていない。例外として、薬師如来は病苦を取り除くために左手に薬壺を持っている。 釈迦如来の両手は、挙げた手のひらを前に向け「恐れなくてもよい」ことを示す施無畏(せむい)印や、「願いを与える」ために手を前に差し出した与願(よがん)印、両方の手のひらを腹の前に重ねた定(じょう)印などがよく見られる。他の様々な如来も、この釈迦如来の姿がモデルになっていて、悟りを開いた慈愛に満ちた穏やかな表情を浮かべている。 阿弥陀如来は死への不安を取り除き、「南無阿弥陀仏」と唱えることにより、すべての人を極楽浄土に導くとされる仏。極楽往生には上品上生(じょうぼんじょうしょう)から下品下生(げぼんげしょう)までの9つの段階(九品=くぼん)があって、阿弥陀如来は臨終の際に生前の信仰や善行の深さによって、それぞれのランクに導く。阿弥陀如来はその九品を両手の印相(指の形)で示している。いわゆる「九品来迎印」である。親指と人差し指を合わせて輪を作るのが上生、親指と中指で作るのが中生、親指と薬指で作るのが下生。坐像では上品上生が、立像では上品下生の印相が多い。 薬師如来は医薬を司る仏で、様々な病気を治し、命を延ばしてくれるとされ、日本でも飛鳥時代から信仰されてきた。 平安時代初め、空海によって中国からもたらされたインド発祥の「密教」は、日本では真言宗として広まっていった。密教の本尊であり、多くの真言宗寺院の本尊とされているのが大日如来だ。密教の教えによると、大日如来は宇宙全体の中心にいる最高の存在であり、宇宙の真理そのものという壮大なスケールの存在。また、すべての仏は大日如来の化身であるとされる。その姿は他の如来と大きく違い、頭にはきらびやかな宝冠を被り、首飾りや腕輪といった豪華な装身具を身に付けている。 大日如来は金剛界、胎蔵界の二つの姿を持つ特徴がある。金剛界とは主体、永久不変の世界、胎蔵界とは客体を表現しているとされ、これら二つの世界は別々のものではなく、一体のものであることを表す。二つの姿の大きな違いは「印相」だ。金剛界大日如来は「智」の象徴で、智恵の深さを意味する智拳印を結んでいる。これは左手の人差し指を立て、右手でその指を握る手の形。一方、胎蔵界大日如来は「理」の象徴とされ、瞑想していることを表す法界定印を結んでいる。こちらは腹部の前で左右の手のひらを重ね、両手の親指の先を合わせた形で、座禅で組む手の形に似ている。二つの姿が対になることで、密教の世界観を表現している。 |