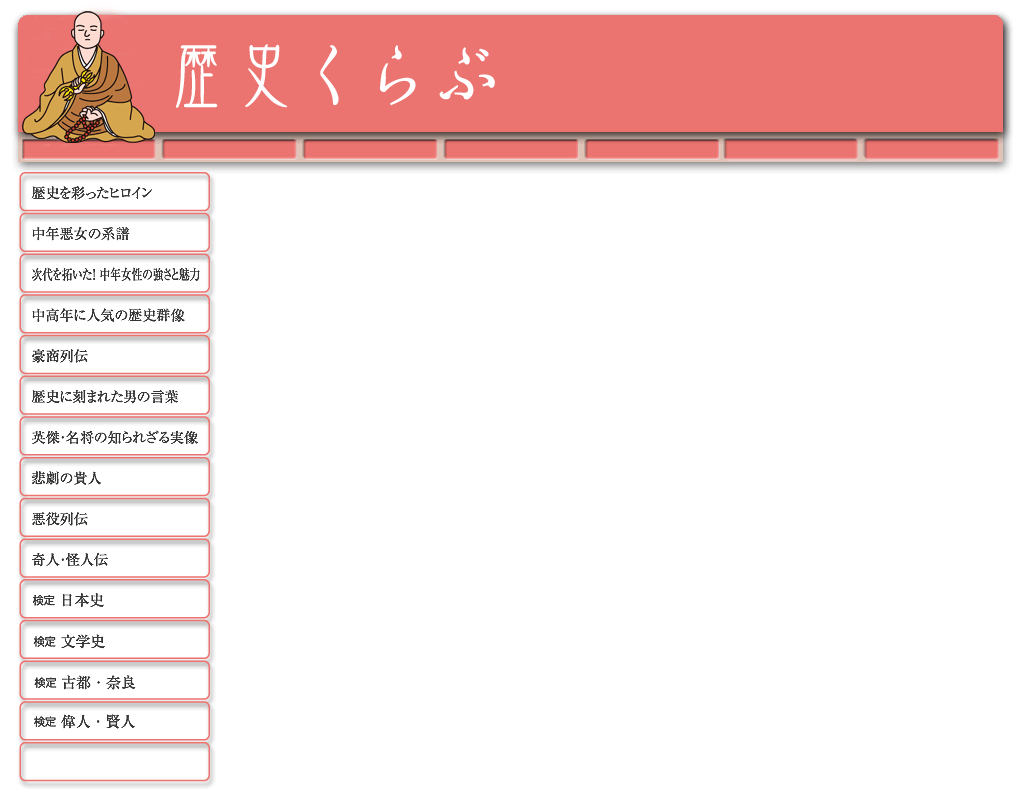
|
仏像ミニ知識
1) 仏像の見方 2「菩薩」の特徴 如来の次に位置づけられるのが「菩薩」。菩薩とは菩提薩_(ぼだいさった)の略。菩提は悟り、薩_は衆生(この世のすべての生き物)を示し、菩薩は悟りを求めて修行している仏のことをいう。自ら修行しつつ、人々を救済する役割を果たす。多くの人々の救済を目指す大乗仏教の発展に伴って、様々な菩薩が生まれるようになった。菩薩のモデルは出家前の釈迦の姿を表したもので、額に白毫(びゃくごう、白く長い毛が渦を巻いて生えている)があるなど、如来との類似点もあるが、姿は古代インドの王族。現世の虚飾や欲をまだ捨てていない。そのため、髪を結い上げ、装身具で飾り立てた華やかな姿が一般的。菩薩の代表格は弥勒菩薩と観音菩薩。観音は人々が救いを求める声を感じ取り、その願いに応じて姿を変える。本来の姿を聖(しょう)観音と呼び、十一面観音や千手観音を変化(へんげ)観音と総称する。 菩薩は如来の衆生救済の仕事を補佐する役目を果たすと考えられている。そのため、如来の脇侍として仕えるようになり、釈迦三尊像や阿弥陀三尊像など、三尊形式で表されるようになった。三尊像では中心になる如来と両脇に従う菩薩の組み合わせが決まっており、釈迦如来には文殊菩薩と普賢菩薩、阿弥陀如来には観音菩薩と勢至菩薩、薬師如来には日光菩薩と月光菩薩が従うことになっている。 菩薩は温和な表情が一般的で、髪を美しく結い上げる。これを髻(けい)と呼ぶ。頭の周りに天冠台と輪をかぶり、その上に宝冠を載せる。胸元は瓔珞(ようらく)と呼ばれるネックレスで彩り、耳には耳_(じとう)というイヤリングを、手首や腕、足首には、それぞれ腕釧(わんせん)、臂釧(ひせん)、足釧(そくせん)と呼ばれる輪状の飾りをつける。 代表的な観音菩薩を例に、その特徴をみると慈悲をもって自在に救いの手を差し伸べることから、観世音菩薩、観自在菩薩ともいわれ、現世利益をもたらすとして広く信仰を集めてきた。 菩薩の台座として多いのは、蓮華をかたどった蓮華座で、持ち物の蓮華と同様、清らかさや尊さを象徴する。 |