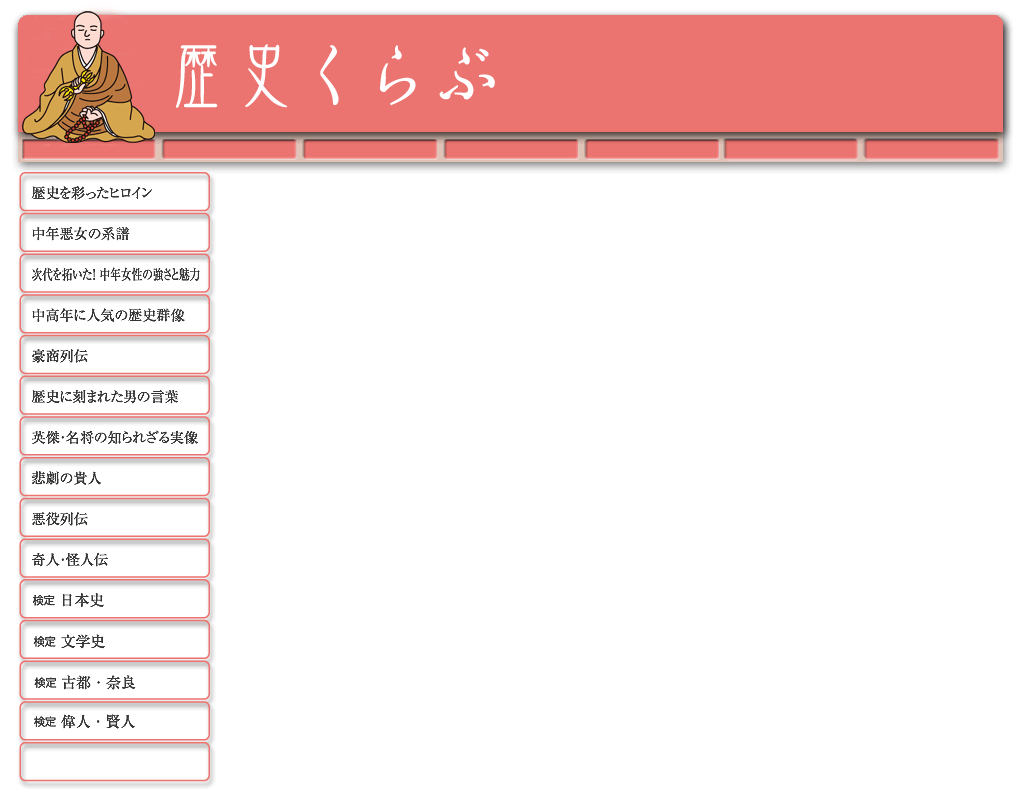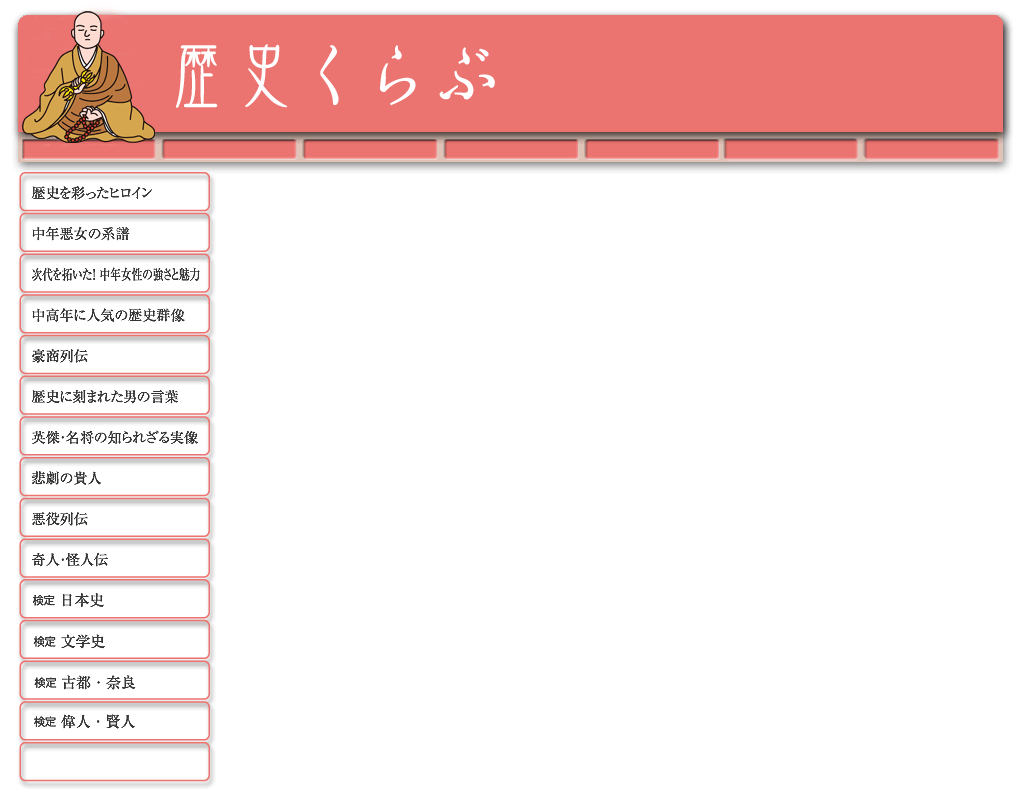『英傑・名将の知られざる実像』
藤原能信 摂関政治から院政への橋渡し役を演じた陰の実力者
藤原能信(よしのぶ)といっても、一般にはあまり知られてはいない。彼は藤原摂関政治の生みの親、藤原道長の子だ。父の道長亡き後、王朝社会の陰の実力者となり、表舞台に出ることはなかった。だが、皮肉なことに彼自身は、そうした意識を持っていたのかどうかは分からないが、計らずも摂関政治から院政への橋渡し役を演じた人物だ。平安時代の政治史の節目を彩る藤原氏のキーパソン、藤原氏北家の礎を築いた藤原冬嗣、そして天皇の外戚として、まさに我が世を“謳歌”した道長の二人に比べると、彼の地位は大納言どまりで、随分見劣りする。しかし、この時代の真の主役は、藤原頼通や教通ではなく、間違いなく能信だった。
藤原能信は藤原道長の四男、母は源明子。官位は権大納言で、春宮大夫を務めたが、頼通・教通らと比べると、随分地味なものだ。生没年は995(長徳元)〜1065年(康平8年)。
父・道長には主な夫人が2人いた。頼通・教通を産んだ源倫子(左大臣源雅信の娘)と、能信の母・源明子だ。倫子は道長の最初の妻であると同時に、当時の現職大臣の娘で、道長の出世の助けになったのに対し、明子の父高明は同じ左大臣でもすでに故人で、しかも「安和の変」で流罪になった人物だった。そのため、倫子の子供たちは嫡子扱いを受けて出世を遂げたのに対し、明子の子供たちはそれ以下の出世に限られていた。
そこで、能信の他の兄弟は頼通と協調して自己の出世を図ろうとした。ところが、能信はそれを拒絶し公然と頼通と口論して、父の怒りを買うことさえあった。こうした姿勢が結果的に出世の途を閉ざしたのか、能信は1021年(治安元年)、正二位権大納言昇進を最後に、その後は官位の昇進をみることはなかった。彼はあくまでも「ゴーイング・マイウエイ(わが道を行く)」の姿勢を貫き通した。もっといえば、彼は開き直って、異母兄弟との出世競争の不利は十分承知のうえで、大胆にも対立陣営に身を置いたのだ。
1037年(長元10年)、後朱雀天皇の中宮(後に皇后)に禎子内親王(後の陽明門院)が決まると、その側近である中宮大夫に能信は任じられた。実はすでに実力者の頼通の養女、_子が天皇の新しい中宮として入内することが確定しているにもかかわらず、あえてその対立陣営のトップに立ったのだ。そして、彼は禎子内親王所生の尊仁親王(後の後三条天皇)の後見人を引き受けることになった。ここで彼は異常な粘り強さをみせる。1045年(寛徳2年)に後朱雀天皇が重体に陥ると、彼は天皇に懇願して、後を継ぐ後冷泉天皇(親王の異母兄)に対して「尊仁親王を皇太弟にするように」という遺言を得たのだ。
しかし世間ではここに至っても、後冷泉天皇には頼通・教通兄弟がそれぞれ自分の娘を妃に入れており、男子が生まれれば皇太子は変更されるだろう−と噂していた。また、それだけに尊仁親王やその春宮大夫となった能信への周囲の眼は冷たいものがあり、現実に親王が成人しても妃の候補者が決まらなかった。有力貴族が実力者の頼通・教通兄弟の敵になることを恐れて、娘を妃に出すことを遠慮したためだ。そこで、今度は能信はやむを得ず、自分の養女(妻祉子の兄である藤原公成の娘)、藤原茂子を妃に入れ、「実父の官位が低すぎる」という糾弾を引き受けることで、辛うじて「皇太子妃不在」という異常事態を阻止したのだ。
これほど献身的にサポートし、以後20年にわたり春宮大夫として尊仁親王の唯一の支持者であり続けた能信だが、悲しいことにその“果実”を自ら手にすることはできなかった。彼は、恐らく夢にまで見たであろう、親王の即位を見ることもなく、しかも右大臣・藤原頼宗(能信の同母兄)の急死で後任大臣への道が開かれたにもかかわらず、その6日後にその生涯を閉じてしまうのだ。
だが、その3年後に後冷泉天皇が男子を遺さずに死去すると、尊仁親王が後三条天皇として即位、続いて茂子の息子の白河天皇が即位した。亡き能信の悲願が達成されたわけだ。そして、後三条天皇は能信の養子で、養父の死後に春宮大夫を継いだ藤原能長(実父は頼宗)を内大臣に抜擢した。また白河天皇は能信に太政大臣の官を遺贈、必ず「大夫殿」と呼んで、生涯尊敬の念を忘れることはなかったと伝えられている。まさに、能信の長年にわたる労苦が報われたのだ。
能信に果たして摂政関白への野心があったか否か、定かではない。だが、後三条・白河天皇による政治とその後の「院政」の開始は、能信の人生に暗い影を落としてきた摂関家による摂関政治を終焉に導いたことは確かだ。
(参考資料)永井路子「望みしは何ぞ」、笠原英彦「歴代天皇総覧」